現在、ベトナム人技能実習生は国籍別で最大を占め、製造業・食品加工など幅広い現場で重要な役割を担っています。しかし近年、応募者層の変化・円安の影響・制度改革(育成就労制度への移行)など、ベトナム人技能実習生を取り巻く環境は大きく動いています。
関連情報:技能実習制度とは?仕組み・職種・人数制限・育成就労制度との違いまで徹底解説
本記事では、ベトナム人技能実習生の特徴、現状の変化、そして今後の制度動向を整理し、受入れ企業が押さえるべきポイントを解説します。
外国人採用必読書 ベトナム 受入れ前にこの一冊
- この資料でわかること
- ・ベトナム人技能実習生の特徴
- ・ベトナムにおける技能実習人気
- ・ベトナムの経済発展の技能実習への影響
- ・これからも受け入れ続けるために必要なこと ・・・等
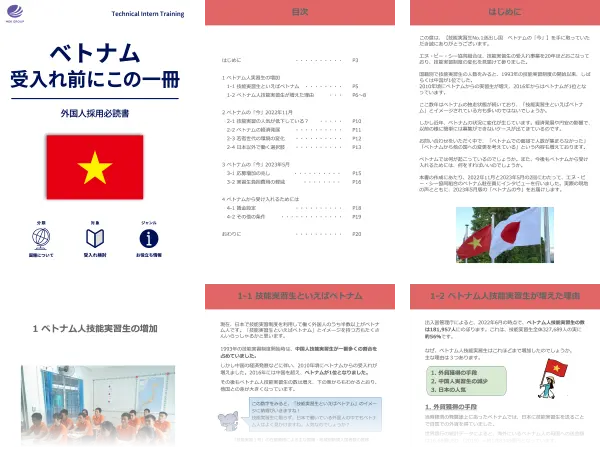
エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする
※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。
なぜベトナム人技能実習生は日本で最も多いのか?【背景とデータ】
過去10年間で、日本で働くベトナム人の数は大幅に増加しました。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によれば、ベトナム人は技能実習だけでなく、留学生や特定技能など、さまざまな在留資格で日本に滞在しています。
⇒送出国ベトナムがわかる資料をダウンロードする(無料)
主要送出国は中国からベトナムへ
かつては中国人技能実習生が大多数を占めていましたが、中国の経済発展に伴い2013年頃から減少に転じ、2016年にはベトナムが送出国として1位となりました。さらに、2017年の技能実習法施行により職種の拡大や最長在留期間の延長が行われ、ベトナム人技能実習生の受入れ拡大を後押ししました。この法改正により、優良な監理団体・実習実施者であれば最長5年間の受入れが可能となり、企業側にとっても技術移転を通じた長期的な関係構築がしやすくなりました。
ベトナム政府の労働輸出政策と経済的背景
ベトナム政府は国家戦略として「労働輸出(海外就労)」を推進しており、海外で働く労働者からの送金がベトナム経済に大きく貢献しているといわれています。ベトナム労働・傷病兵・社会問題省傘下の海外労働管理局(DOLAB)によれば、近年は年間15万人前後が海外での就労を選択しており、その主要な渡航先として日本、韓国、台湾が挙げられます。
国内の平均月収は約500〜600万ドン(約3~4万円前後)とされていますが、地域や職種により差があり、都市部では700万ドン前後となることもある一方、地方部では依然として日本との所得格差が存在するため、「短期間で技術を修得し、収入を得たい」という動機を持つ人材が多く見られます。特に農村部出身者にとっては、海外就労が家族の生活向上につながる重要な機会と位置づけられています。
日本は治安が良く、生活環境や教育面でも信頼が高いことから、韓国や台湾と並んで人気の高い就労先のひとつとなっています。また、日本企業の技術力やものづくりの精神に対する憧れも強く、「日本で学んだ技術を母国に持ち帰りたい」という希望を持つ若者も少なくありません。
ベトナムの親日感情と高い学習意欲
ベトナムは日本のODA(政府開発援助)の主要受益国のひとつであり、長年の協力関係から親日国として知られています。ハノイやホーチミンには日本企業が多数進出しており、日本語学習熱も高まっています。また若年層の人口比率が高く、真面目で学習意欲の高い人材が多いのも特徴です。ベトナムの平均年齢は30代前半とされ、労働力人口が豊富であることも、日本企業にとって魅力となっています。
「日本の技術を学びたい」「家族のために成長したい」といった前向きな考えが強いため、技術移転の目的に合致した人材が集まりやすい環境にあります。また、儒教的な価値観が根付いており、目上の人を敬う文化や、集団での協調性を重んじる傾向も、受入れ企業との親和性を高めています。
⇒親日国ベトナムがよくわかる資料をダウンロードする(無料)
ベトナム人技能実習生の特徴と受入れ時のポイント
ここではベトナム人技能実習生の特徴と、受入れを成功させるポイントをお伝えします。
⇒ベトナム人技能実習生の特徴がわかる資料をダウンロードする(無料)
ベトナム人の国民性・気質と職場での特徴
ベトナム人は総じて勤勉で責任感が強く、器用な作業が得意だと評価されています。特に、細かい手作業や繰り返しの業務において、高い集中力と丁寧さを発揮します。縫製や電子機器組立など、集中力と丁寧さが求められる業種で高い適性を示す傾向があり、食品製造業においても、ベトナム人技能実習生の技能習得の速さや品質管理への意識の高さが評価されています。
また、家族を大切にする文化が根付いており、「両親のために働く」という価値観が強い点も特徴的です。技能実習生の多くが、母国に残る家族へ仕送りしており、その責任感が業務への真摯な姿勢につながっているともいえます。
一方で、個人主義的な側面もあり、自分の意見をはっきりと主張することもあります。日本人のように「察する」文化に慣れていないため、暗黙の了解や曖昧な指示は伝わりにくい、という点には注意が必要です。
コミュニケーションでの留意点と定着率を高めるコツ
日本人と比べて感情を表に出しやすい傾向があり、注意する場面では「人前を避け、個別に伝える」などの配慮が求められます。ベトナムでは「面子(メンツ)」を重んじる文化があり、他の技能実習生の前で叱責されることは大きな屈辱と受け止められることがあります。また、日本的な「あうんの呼吸」は通じにくいため、具体的な指示・期日・手順を明確に伝えることが重要です。作業指示書をベトナム語で用意する、手順書に写真や図を用いるなど、分かりやすい表現を心掛けることで指示も伝わりやすくなります。
⇒現場での指導方法がよくわかる|実習指導員の活躍事例(無料ダウンロード資料)
さらに、ベトナム人は成果を認められることでモチベーションが向上する傾向があります。修得状況を可視化し、定期的に承認や評価を伝えることで、良好な関係を築くことができます。「できたことを褒める」「成長を認める」といったポジティブな評価を本人に実際に伝えることで、技能実習生の意欲もさらに向上していきます。
定期的な面談や、母国語でのフォローアップも有効です。監理団体や通訳スタッフと連携し、技能実習生の不安や悩みを早期に把握することで、トラブルの未然防止にもつながります。
賃金・労働条件で注意すべきポイント
技能実習生にも労働基準法や最低賃金法が適用されるため、最低賃金の遵守はもちろん、日本人との間で不合理な待遇差が生じないようにする、いわゆる同一労働同一賃金の考え方を踏まえることが求められます。
また、労働条件通知書をベトナム語で交付し、勤務時間・手当・休日などを明確に説明することが、誤解や不満の防止につながります。特に、残業や休日出勤の扱いについては、事前に丁寧な説明を行うことが求められます。
賃金の支払い方法や控除項目(寮費、光熱費、食費など)についても、透明性を保つことが重要です。給与明細をベトナム語で作成する、控除の根拠を明示するなど、技能実習生が納得できる形で情報を提供することが、信頼関係の構築につながります。
さらに、社会保険(厚生年金、健康保険)についても、制度の内容や脱退一時金の仕組みを説明しておくことで、帰国時のトラブルを防ぐことができます。
⇒技能実習生の賃金設定がよく分かるダウンロード資料(無料)
生活面でのサポート体制
受入れ企業には、技能実習生の生活面でのサポートも求められます。住居の確保、日常生活のオリエンテーション、病院への同行、地域住民との交流支援など、技能実習生が安心して生活できる環境を整えることが重要です。
特に来日直後は、日本の生活習慣や公共交通機関の利用方法、ゴミの分別ルールなど、基本的な生活指導が必要となります。監理団体と連携し、技能実習生が孤立しないようなサポート体制を構築することが求められます。
また、技能実習生同士のコミュニティ形成を支援することも有効です。同じ職場や地域のベトナム人技能実習生が交流できる機会を設けることで、ストレスの軽減や情報共有が進み、定着率の向上につながります。
⇒生活面でのサポートが光る|生活指導員の活躍事例(無料ダウンロード資料)
ベトナム人技能実習生を取り巻く現状と今後
技能実習生の送出国として確固たる地位を築いたベトナムですが、近年その状況に変化が生じています。現在の状況と、これからも技能実習生を受け入れ続けるためのポイントを見てみましょう。
⇒送出国ベトナムの現状がわかる資料をダウンロードする
ベトナム国内の経済発展による応募者の変化
近年、ベトナム国内の経済成長と雇用機会の拡大により、海外就労を希望する若者の間に変化がおきています。世界銀行の報告によれば、ベトナムのGDP成長率は年間5〜7%程度で推移しており、製造業やサービス業を中心に雇用が拡大しています。
都市部では給与水準も上昇しており、国内で安定した仕事を得られる環境が整いつつあります。特にハノイやホーチミンなどの大都市では、外資系企業の進出が相次ぎ、英語や日本語ができる人材の需要が高まっています。
また、大学進学率の上昇により、高学歴層は日本よりも母国でのホワイトカラー職を志向する傾向が見られます。かつては「日本で働くこと」が憧れの対象でしたが、現在では「選択肢のひとつ」として捉えられるようになっています。
このような環境変化により、日本の技能実習制度への応募者層も変化しつつあり、都市部の高学歴層よりも、地方出身者や職業訓練校卒業者が中心となる傾向が見られます。
円安・渡航費用・失踪問題など受入れをめぐる課題
2024年以降の円安により、日本で働いても母国への送金額が目減りする状況が続いています。かつては1円=180~200ドン前後で推移していた為替レートが、2025年現在は1円=170ドン前後となっており、実質的な収入が減少しています。
さらに、渡航前に一定の手数料を送出機関に支払うケースもあり、借金を抱えて来日する技能実習生も少なくありません。この費用には、日本語教育費、健康診断費、ビザ申請費などが含まれますが、一部の送出機関では不透明な請求が行われているとの指摘もあります。労働条件や賃金に関する認識のずれが生じた場合、「期待と現実のギャップ」が失踪につながるケースもあります。厚生労働省の統計では技能実習生の失踪者数は年間数千人規模で推移しており、ベトナム人も一定数含まれています。
制度運用における課題と改善の方向性
技能実習制度は「発展途上国への技術移転」を目的とした国際貢献制度です。しかし、実態としては人手不足を補う手段として活用されてきた側面もあり、制度趣旨と現場のニーズとの間にずれが生じてきました。
新たな制度「育成就労制度」と特定技能の活用
政府は、技能実習制度から新しい制度へ移行する方針をすすめ、2027年4月1日より育成就労制度を施行すると閣議決定しました。育成就労は、一定期間(原則3年)の就労を通じて特定技能1号水準にまで人材を育成することを想定した制度であり、特定技能への移行と組み合わせて活用されることが見込まれています。
これまで多くの特定技能人材を輩出してきたベトナムにとって、特定技能への明確な足がかりと捉えられる育成就労制度は活用しやすい制度だといえるでしょう。また、現在ベトナム人特定技能が活躍している受入れ企業にとっても、同国の人材を受け入れる体制を継続できるため、技能実習以上にベトナム人材の受入れにインセンティブを感じる制度であるといえるでしょう。
今後は、技能実習から育成就労、さらに特定技能へとキャリアをつなげていくことを前提に、ベトナム人材を中長期で育成・活用するモデルが主流になっていくと考えられます。
⇒技能実習と育成就労の違いが判る資料をダウンロードする(無料)
監理団体の選定が成否を分ける
技能実習や育成就労を成功させるためには、信頼できる監理団体の選定が不可欠です。監理団体は、実習計画の作成支援、定期的な監査、技能実習生からの相談対応など、重要な役割を担っています。
優良な監理団体を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 一般監理事業の許可を受けているか(優良要件を満たしている)
- 技能実習生の母国語に対応できる体制があるか
- 過去の実績や実習生の定着率はどうか
- 監査や訪問指導を適切に実施しているか
- トラブル発生時の対応体制が整っているか
育成就労制度では、現在の監理団体は「監理支援機関」という位置づけに変わりますが、企業や外国人材を支援するという根本的な役割は変わりません。むしろ、責任範囲や要件が明確化されることで、「どの支援機関を選ぶか」がこれまで以上に重要になります。
⇒監理団体の仕事がわかる資料をダウンロードする(無料)
まとめ
ベトナム人技能実習生は、勤勉で協調性が高く、技術移転の目的に適した人材として日本企業に受け入れられてきました。
一方で、ベトナム国内の経済成長・円安・制度改革など、外部環境の変化により、従来の受入れモデルだけでは対応が難しくなりつつあります。
制度動向を踏まえながら、柔軟に受入れ体制を見直すことが、受入れ企業にとっての持続的な競争力につながるでしょう。技術移転という本来の趣旨を尊重しつつ、技能実習生と企業の双方にとって有益な関係を築くことが、今後ますます重要となります。ベトナム人技能実習生の受入れについて、ご不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
⇒エヌ・ビー・シー協同組合に問い合わせてみる
参考情報
- 出入国在留管理庁「在留外国人統計」
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」
- JETRO「ベトナムの労働市場動向」
- 厚生労働省「技能実習制度運用要領」
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省「海外労働管理局(DOLAB)」
- ※本記事は2025年時点の情報をもとに作成しています。最新の制度動向については、各行政機関の公表資料をご確認ください。
