これから技能実習生を受け入れようとお考えの企業様、ご担当者様から
「技能実習生を受け入た時によくあるトラブルや問題は何ですか?」
という質問をいただくことがあります。
※関連情報:【徹底解説】外国人技能実習生受入れの流れ
今回は、技能実習生の受入れでよくある問題を
の2つに分け、解決方法をご紹介していきます。しっかり不安を解消して受入れに臨みましょう。
実際にあったトラブルをご紹介 技能実習生のトラブル&対応策
- この資料でわかること
- 技能実習生のトラブル事例
- トラブル事例ごとの対応例
- トラブルの原因と対応策
- 技能実習生の相談記録と対応例
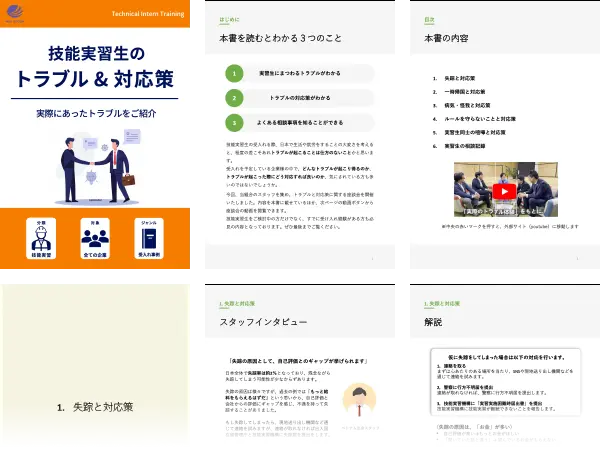
エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする
※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。
技能実習生の受入れで起きる問題は2パターン
これから技能実習生を受け入れようとお考えの企業様。
初めての技能実習生の受入れには大なり小なり何かしらの問題やトラブルはつきものです。しかし事前に想定し備えておくことで、無用なトラブルを回避できますし、また問題の早期解決も期待できます。
トラブルが続くと技能実習生の失踪というケースも起こり得ます。そのようなケースをさけるためにも早期の対策が不可欠です。万一失踪が起きた時の対策についてはこちらのページで詳しく解説しています。
関連情報:技能実習生の失踪【ペナルティと防止策】
受入れ企業に原因があるケース、技能実習生に原因があるケースの2パターンに分け、技能実習生の受入れで起こりうる問題について、事前に確認していきましょう。
⇒技能実習の現場でよくあるトラブル&解消法が分かるダウンロード資料(無料)
受入れ企業に原因があるケース
受入れ企業に原因があるケースは、
- 「賃金に関する問題」
- 「実習生への対応に関する問題」
この2つが多く挙げられます。順に見ていきましょう。
賃金に関する問題
技能実習生の受入れ企業に原因があるケースで「賃金に関する問題」として特に多いのが
- ・最低賃金を守っていない
- ・残業代を支払っていない
- ・深夜・休日勤務に対する割増賃金を払っていない
以上の3つです。
技能実習制度は技術の移転が目的とはいえ、技能実習生と受入れ企業は雇用契約を結びますので、当然ですが労働基準法に沿った内容で技能実習を行うことになります。
賃金をキチンと支払わないのは、故意であれうっかりミスであれ、雇用者にあるまじき行為です。
⇒技能実習生の賃金設定がよく分かる資料をダウンロードする
技能実習生への対応に関する問題
「実習生への対応に関する問題」では、主に技能実習生に対する暴力があげられます
実習の現場で「指導」の名のもとに暴力をふるう、必要以上の暴言を吐き高圧的な態度で接するなどの直接的な暴力もありますが、実習中に怪我をしたのに労災隠しのために病院に行かせない、自由を奪うためにパスポートを取り上げるといった間接的な暴力もあります。配属間もない時にまだ理解出来ていないであろう日本のマナーを当然のものとして押し付けるのも、暴力の一種といえるかもしれません。
これら受入れ企業に原因があるケースを見てみると、この企業は受入れを行うべきではなかったといわざるを得ません。また技能実習生だけでなく日本人従業員にとっても、この企業は恐らくあまり働きやすい職場では無いのではないでしょうか。
現在、受入れ企業の認定取り消し件数が累計600件に迫ろうとしています。認定取り消し事由について、こちらのページで詳しく解説しています。
※関連情報:ご存じですか?技能実習591件の受入れ停止処分
技能実習生に原因があるケース
続いて、技能実習生に原因があって問題となるケースを見てみましょう。
⇒技能実習生のトラブル対応策がよく分かる資料をダウンロードする
実習の現場での問題
実習の現場での問題は、多くの場合日本語力の低さが原因となっています。
実習指導員が指示を出すと元気よく「ハイ」と返事をするものの、ほとんど理解しておらず全く違った作業を行なっていた、分からないことがあっても意思の疎通ができず、質問もしないまま間違った内容で作業していた等、コミュニケーションが取れないことを原因とした問題です。
コミュニケーションが取れないために日本人との交流もなく、技能実習生同士でしか話しをしないなど、風通しのよい環境とはいえない実習現場となることもあります。
エヌー・ビー・シー協同組合のサポートスタッフが定期訪問した際に、言葉に関するトラブルを企業独自の取り組みで克服したお話をうかがいました。現場でのトラブル解決事例はこちらのページで解説しています。
※関連情報:【技能実習現場のトラブル】受入れ企業の解決事例
私生活での問題
技能実習生の私生活での問題は、大きく分けて3つあります。
まずは寮周辺住民との問題です。
ゴミを出す日が決まっているのに曜日を守らずに出してしまったり、粗大ゴミや分別ゴミのルールを守らずトラブルになることがあります。また、夜中にも関わらず寮で大騒ぎをして苦情が寄せられるといったこともあります。
続いて交通事故です。
寮と実習先を自転車で往復していた道すがら、信号を確認せずに道路を渡ってしまい車と接触してしまった、狭い道をスピードを落とさず走行し出会いがしらに歩行者とぶつかってしまったなど、被害・加害の両方があります。
最後が事件に加担するケースです。
野菜や動物を盗んだといったニュースが報道されることもありますが、徒党を組んでの窃盗や銀行口座やパスポートの売買、失踪しての不法就労も大きな問題です。
⇒技能実習生のよくあるトラブルとその対応が分かる資料をダウンロードする
受入れ前に解決策を確認
技能実習に関する問題を、受入れ企業を原因とするケースと技能実習生に原因があるケースに分けて見てきました。
まず、受入れ企業に原因があって問題になっているケースは、簡単ではないでしょうが、改善への強い意思があれば状況が好転していくことも期待できます。もしも該当する問題があるようなら、この後紹介する解決策を参考に是非改善していきましょう。
技能実習生に原因があり問題となっているケースも、実は受入れ企業の対応でほとんどの場合解決することができます。解決策を順に見ていきましょう。
解決策:受入れ企業に原因があるケース
受入れ企業に原因がある場合は、改善にはかなりの努力が必要になるかもしれませんが、技能実習生を受け入れる前にしっかり改善しておきましょう。
解決策:賃金に関する問題
故意に賃金を払わない、といった場合は、本当に心を入れ替えていただくしかありませんが、たまたまのうっかりで正しい賃金を支払わなかった、ということがあるかもしれません。
タイムカードを使用する、給料計算ソフトを導入するなど、人的なミスが発生しにくい仕組みを導入しましょう。また、技能実習生自身でも給料明細を確認できるようにすれば、もしものミスもすぐに見つけられるでしょう。
監理団体のサポートスタッフに確認を依頼するのも解決策のひとつです。
⇒技能実習生の賃金設定がよくわかる無料ダウンロード資料
解決策:技能実習生への対応に関する問題
例えば建築現場等、万一の時に大怪我となってしまうような実習現場においては、大きな声で怒鳴ったり注意のために手が出てしまったり、といったことがあるかもしれません。これは技能実習生だからということではなく、日本人従業員が相手であっても、恐らく同様の対応となるのでしょう。
危険を伴う現場であれば、ある程度は仕方がない・・ということはありません。
現場の状況を技能実習生と事前にしっかり共有し、もしもの事態に陥らないようしっかり準備しましょう。
それでも回避できない危険に直面するケースがあるかもしれませんが、日頃から信頼関係をしっかり築き、危機管理の情報を共有しておけば、その際の大声は「暴力」とは認識されることはないでしょう。
技能実習生に理解できない日本のマナーを押し付けるという行為は、恐らく自分より弱い者に対してそのような態度を取る社風があるのでしょう。そのような現場環境は、どう考えても健全とはいえませんし、日本人従業員にとっても居心地のいい職場ではありません。しっかり従業員と向き合い、社内環境の刷新を図りましょう。
労災隠しのために病院に行かせない、自由を奪うためにパスポートを取り上げるといった行為は犯罪行為ですので、自浄効果が期待できないようであれば、労働基準監督署や信頼できる監理団体に相談しましょう。
解決策:技能実習生に原因があるケース
それでは、技能実習生に原因がある場合の解決策を見ていきましょう。
解決策:実習の現場での問題
実習の現場でコミュニケーションがとれない、指示が伝わらない、日本人との交流がない、同じ国籍の技能実習生だけで固まってしまう・・配属されてすぐの技能実習生はなかなか日本語を上手に使うことはできませんので、放っておけばこのような状況に陥ってしまうかもしれません。
このような問題を「言葉の壁」と捉えてしまうと対応が難しく感じられますが、技能実習生の指導も「日本人への指導法の延長線上にある」と考えるとスムーズに落とし込むことができるのではないでしょうか。
配属された技能実習生は、念願かなって日本にやってきました。やる気に満ち溢れています。技能実習生たちのやる気を削ぐことなく、早く実習の現場に慣れさせてあげましょう。はじめのうちは日本語でのやり取りは難しいかもしれませんが、日本人の従業員から積極的に話しかけてあげましょう。具体的な言葉の意味は分からなくても、好意的な態度は伝わりますし、信頼関係も築くことができます。
技能実習指導員がその先陣を切って積極的に日本語で話しかけていけば、実習現場の雰囲気も良くなりますし技能実習生の日本語の習得も早くなることでしょう。
多国籍の技能実習生を受け入れるのもひとつの方法です。社内公用語が日本語になりますので日本語を使う機会も増え、日本語能力も上がりやすくなります。
⇒コツを掴めば日本語は簡単!【無料ダウンロード資料】
実習の現場では技能実習指導員が先頭に立ち、日本人への指導方法に「ちょっとした工夫と気遣い」をプラスアルファした指導を技能実習生に施すことで、技能実習生の実習に対する意欲も向上していくことでしょう。
⇒実習指導員の「指導方法の実例」を掲載した資料をダウンロードする
解決策:私生活での問題
実習の現場を離れた技能実習生の私生活での問題には、どう対応すればよいでしょうか。
まず寮周辺住民との問題です。
技能実習生は入国前講習と入国後講習で、日本語だけでなく日本で生活する上でのマナーや文化を学びます。しかしその期間では完全に習得することはできませんし、配属された先では学んだルールと違うこともあるでしょうから、初めのうちはどうしてもトラブルになるケースが多くなります。そんな時も、事前にトラブルになりそうなポイントを押さえておけば問題は最小限で済みます。
ゴミ出し問題と騒音問題、住人でない外国人による寮への頻繁な出入り等はよくあるトラブルです。ゴミ出しルールの徹底や、夜間の騒音の抑制、不特定多数の住人の出入りは控える、加えて近隣住民との挨拶を欠かさないなど、ポイントを押さえて指導していきましょう。
⇒実習生のトラブル対策資料を読む
次に交通事故対策です。
寮から実習先への往復に自転車を使用する技能実習生は多いですが、二人乗りをしない、夜間はライトを点けるなどのルールの確認だけでなく、通勤経路での危険な個所、注意すべき個所も伝えておきましょう。警察署で外国人を対象にした交通ルール教室が行われることもありますので、最寄りの警察署でそういった行事があれば積極的に参加することもお勧めします。
最後に事件に関わる問題です。
窃盗などの明らかな犯罪行為はもっての外ですが、「自分の国の田舎ではみんなやっていた」行為、例えば池の鯉を捕ってしまったり、飼われている鶏を捕まえたりといったこともあるかもしれません。寮の周りの環境によっては「動物をとってはいけない」ということも、しっかり伝えておきましょう。
犯罪行為の片棒を担がされる、銀行口座を売買するといったケースは極端な例にはなりますが、きっかけはSNSでの勧誘が多いといわれています。技能実習生が所持しているSNSのアカウントを日本人従業員がフォローし、日頃からそこを気軽にストレスが発散できる意見交換の場にしておくと、犯罪組織からの接触もおいそれとは行われないはずです。
いずれにせよ私生活での問題を回避するためには、実習での現場と同様に日頃からの密なコミュニケーションが欠かせませんが、特に活躍が期待されるのが生活指導員です。
日本にやってくる技能実習生の多くは20代の若者であるため、生活指導員は「日本における保護者」のような立場として技能実習生と接することが多くなりますが、例えばエヌ・ビー・シー協同組合の受入れ企業の中には、技能実習生の実家と手紙のやり取りをし、技能実習生と家族の両方に安心してもらう試みを行っているところもあります。
生活指導員の「きめ細やかなちょっとした気遣い」で技能実習生の日本での生活も更に有意義なものとなるはずです。
⇒生活指導員の活躍を掲載した無料ダウンロード資料
技能実習生をとりまく環境
2017年11月1日、技能実習制度はそれまでの旧制度から新たに「技能実習法」として改めて制定されました。
新たな技能実習法により、問題のある企業には監査でしっかりとした指導が入るようになりました。監理団体にも監査が入るようになり、悪質な監理団体の場合は認定の取り消しも行われるようになって、技能実習生を取り巻く環境はかなり良くなっているといえます。
技能実習生の受入れでトラブルが発生することもありますが、制度に則り健全な運用をしていれば、ほとんどの場合解決できます。 もちろん簡単には解決が難しいような場合もありますが、わたしたち監理団体にご相談いただければ、解決にむけてしっかりとサポートしてまいります。技能実習生の受入れにご不安な点やご不明な点などありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。
⇒受入れ前に不安や不明点を解決する
