技能実習制度において欠かすことのできない存在である「送出機関」について、その本来の役割をご存じでしょうか? 送出機関を通じて技能実習生を受け入れる仕組みは理解されていても、送出機関が果たすべき役割やその重要性について詳しく知らない方は意外と多いかもしれません。
※関連情報:技能実習制度とは?
技能実習制度を円滑に運用するためには、送出機関の役割を正しく理解することが非常に重要です。万一、悪質な送出機関と提携してしまった場合、知らないうちにトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
そこで今回は、送出機関の役割やその重要性、良い送出機関を選ぶための判断基準について詳しく解説します。
技能実習と送出機関の新しい関係 基礎から学ぶ送出機関
- この資料でわかること
- ・送出機関の役割
- ・送出機関の新定義「外国の準備機関
- ・送出機関の新定義「外国の送出機関」
- ・送出機関の適正化 ・・・等
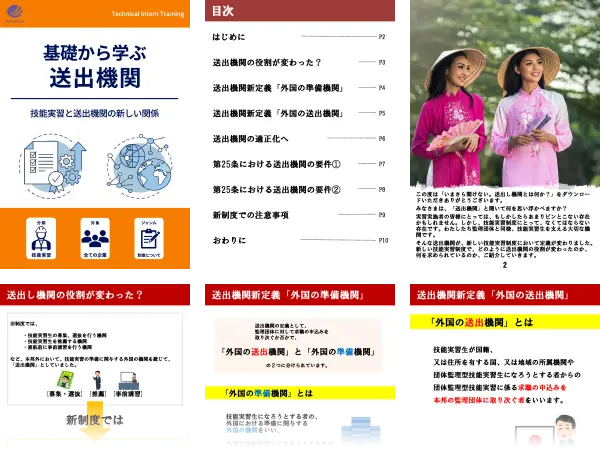
エヌ・ビー・シー協同組合のサポート内容が分かる資料をダウンロードする
※個人情報入力の必要はありません。自動でダウンロードされます。
送出機関とは
2017年11月の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)」の改定に伴い、送出機関の定義も厳格化されました。
旧制度では、技能実習候補生の募集をおこなう・日本への渡航前に事前講習をおこなうなど、技能実習生が日本へやってくる準備にかかわる機関のことを総じて「送出機関」とよんでいました。
2017年の改訂により、技能実習生の申込みを日本の監理団体へ取り次ぐ機関は「外国の送出機関」、それ以外で技能実習生に関わる機関は「外国の準備機関」と定義されました。
⇒送出機関についてよくわかる資料をダウンロードする(無料)
送出機関・準備機関が担う重要な役割
送出機関と準備機関は、「技能実習生の日本への送出し」に関して重要な役割を担っています。主な業務は以下の4つです。
- 1、人材募集
- 2、入国前教育
- 3、申請書類の作成
- 4、入国後のフォローアップ
それぞれの業務について順に見ていきましょう。
⇒送出機関の役割についてよくわかる資料をダウンロードする(無料)
1、人材募集
技能実習として就労を希望する人材を現地で募集します。求人情報や技能実習の目的・内容を適切に説明したうえで、受入れ企業様の求める人材に合わせて候補者を選抜します。
2、入国前教育
日本へ入国するまでの間、技能実習生に対して、日本での生活や実習に必要な日本語教育を施します。また日本での生活に困らないよう、日本の文化やマナー、日本の法律(労働法など)についても教育します。
3、申請書類の作成
パスポートの取得や渡航に必要な手続き(海外旅行保険の加入、税関手続きなど)をサポートします。そのほか、面接終了後にはビザの申請書類作成を監理団体と協力して行います。
4、入国後のフォローアップ
送出機関は技能実習生が日本へ入国した後も、技能実習生の相談に乗りアドバイスをするなどのサポートをします。
長期にわたる異国での生活は精神的な負担となる場合があります。送出機関は、仕事面での悩みだけでなく、生活面の悩みや人間関係のトラブルなど様々な相談に対応し、技能実習生のメンタルケアを行います。
送出機関を選ぶのは監理団体の役割
このように、送出機関は入国前の技能実習生に関わる重要な業務を担っています。送出機関の質が、受入れ後の技能実習生の成長度合いにも大きく関わっているため、技能実習の成功には良い送出機関を選ぶことが不可欠ともいえます。
⇒送出機関の果たす役割がわかる資料をダウンロードする(無料)
ただし、送出機関を選ぶのは、基本的に受入れ企業様ではなく監理団体です。そのため、良い送出機関から技能実習生を受け入れるには、良い送出機関と提携している監理団体を選ぶことが不可欠です。
良い送出機関と提携している、優良な監理団体を選びましょう。
監理団体に確認すべきポイント
監理団体が良質な送出機関と提携しているかどうか、見分けるのは簡単なことではありませんが、良い送出機関は必ずクリアしている4つの項目があります。この4つの項目について監理団体に確認することで、送出機関選定失敗のリスクがかなり軽減されます。
以下の4つの項目について、監理団体の担当者に確認してください。
⇒技能実習が成功する8つのポイントがわかる無料ダウンロード資料
1、政府認定送出機関かどうか確認
送出機関が各国の政府(ベトナムは労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)、タイは労働省雇用局(DOE))から正式に認定を受けているかどうかを確認しましょう。
認定を受けていない機関は、法令違反のリスクがあるだけでなく、技能実習生の管理体制やサポート体制が不十分な可能性があります(※認定機関のリストは、外国人技能実習機構(外国政府認定送出機関一覧)より確認できます)。
2、技能実習生の手数料確認
送出機関は、技能実習生から徴収する手数料等の算出基準を明確に定め、公表し、技能実習生に対して説明し十分に理解させることが義務付けられています。不当な金銭徴収が行われると、技能実習生は多額の借金を抱えた状態で入国することになり、大きな負担となります。また、借金の返済が困難だと感じた場合、技能実習生が失踪してしまうという恐れもあります。
企業様にとっても失踪リスクを減らすために、監理団体に対して「送出機関が適正な費用を設定しているかどうか」確認することが重要です。
3、日本語の教育レベルを確認
技能実習生は、採用決定後から入国までの約5か月間、送出機関で日本語を学びます。この期間にどれだけ日本語を習得するかによって、入国時の日本語力も変わり、配属後の仕事の習熟スピードも大きく変わります。
技能実習の成功のためにも、日本語教育の充実度、日本文化の理解促進、法的保護に関する説明など、研修内容が十分かどうか監理団体にしっかり確認しましょう。
⇒コツがわかれば日本語は簡単!実習生に教えたい日本語習得術がわかる資料をダウンロードする(無料)
4、監理団体との連携状態を確認
監理団体と送出機関の連携がスムーズに行われているかどうかも重要なポイントです。両者の連携が密接であるほど、入国前の教育が充実し、また入国後もトラブル発生時に連携できるなど、技能実習生へのサポート内容にも期待できます。
これら4点について監理団体に確認することで、良い送出機関から技能実習生を受け入れられる可能性が高くなりますし、良い監理団体と巡り合う可能性も高くなります。技能実習の成功のために、しっかり確認しておきましょう。
送出機関の認定要件
送出機関は技能実習生を日本へ送り出すにあたり、一定の要件を満たしている必要があります。要件については技能実習法の規則第25条に定められており、送出機関がやるべきこと、やってはいけないこと、そして有すべき能力が明確に定義されました。
⇒送出機関の要件についてよくわかる無料資料をダウンロードする
【送出機関がやるべきこと】
01、送出機関が所在する地域・国などの公的機関から推薦をうけていること
02、実習制度の趣旨を理解したうえで、実習生を適切に選定して日本へ送り出すこと
03、実習生から受け取る手数料などの費用について、算定基準を明確に定めて公表し、実習生に十分理解させること
04、実習生が技能実習を終えて帰国したときに、習得した技能を適切に活用できるように就職斡旋などの支援をすること
05、帰国した実習生のフォローアップ調査などへの協力に応じること
06、送出機関、またその役員が禁錮刑以上の刑をうけた場合、その執行をうけることがなくなった日から5年以上経っていること
07、送り出し国の法令にしたがって業務をおこなうこと
【送出機関がやってはいけないこと】
01、以下のことを過去5年以内におこなっていないこと
a、技能実習に関連して、実習生やその親族などの財産を管理すること
b、技能実習にかかわる契約不履行に対しての、違約金や財産移転などの契約をおこなうこと
c、技能実習生への暴行・脅迫・自由の制限その他人権を侵害する行為をとること
d、ビザ等の偽造をおこなうこと
【送出機関が有すべき能力】
01、技能実習生を日本の監理団体へ取り次ぐための必要な能力があること
二国間協定について
「二国間協定」とは、日本と技能実習生を送り出す国との間で締結される政府間の取り決めです。これは、技能実習制度の円滑な運営と技能実習生の保護が目的で、「協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)」とも呼ばれます。送出機関のある19か国のうち、外国人技能実習制度の二国間協定を締結している国は16ヶ国です。
原則として、二国間協定を締結していない国からの技能実習の受入れはできません。
送出機関のある国
2025年9月現在、送出機関として19か国が認定されています。
- ・インド
・インドネシア
・ウズベキスタン
・カンボジア
・キルギス(特定技能のみ)
・スリランカ
・中国(二国間協定未締結)
・タイ
・ネパール
・パキスタン
・バングラデシュ
・東ティモール
・フィリピン
・ブータン
・ベトナム
・ペルー(二国間協定未締結)
・ミャンマー
・モンゴル
・ラオス - 【出典:外国人技能実習制度とは|JITCO】
送出機関の数
2025年9月現在、二国間協定を結んでいる16か国において、認定されている送出機関数は以下の表の通りです。
| 国 | 認定送出機関数 |
| インド | 23 |
| インドネシア | 544 |
| ウズベキスタン | 9 |
| カンボジア | 116 |
| スリランカ | 142 |
| タイ | 55 |
| ネパール | 498 |
| パキスタン | 90 |
| バングラデシュ | 91 |
| 東ティモール | 1 |
| フィリピン | 336 |
| ブータン | 1 |
| ベトナム | 454 |
| ミャンマー | 517 |
| モンゴル | 71 |
| ラオス | 30 |
数多くの技能実習生を送り出している国ほど、多くの認定送出機関があるのがわかります。ただ、上の表に含まれないもの、つまり認定されていないにもかかわらず、送出機関と名乗っているケースもあります。監理団体に対して、提携している送出機関がしっかり認定を受けているかどうか確認しておきましょう。
送出機関で特殊な手続きが必要になる国籍
技能実習制度の円滑な運用と技能実習生の保護を目的として、日本と送出国間で二国間協定を締結していますが、協定の内容は国によって異なります。
フィリピンとベトナムにおいては、技能実習生の受入れに特殊な手続きが必要となっていますので、それぞれの国について詳しく見てみましょう。
フィリピン
フィリピンは、海外で働く労働者を保護し公正な労働環境を確保するために、様々な保護政策を行っています。
技能実習生の受入れには、DOLE(労働雇用省)、DMW(海外労働者省)、MWO(海外労働事務所)が深く関わっており、フィリピン政府の規定から技能実習生は厳格に管理されます。
⇒送出し国フィリピンがよくわかる資料をダウンロードする(無料)
フィリピン技能実習生受入れの流れ
1、MWO(旧POLO)への認証申請
受入れ企業はMWOへ認証申請を行い、審査を受けます。申請が許可された企業のみフィリピン技能実習生の受入れが可能です。
2、DMW(旧POEA)への推薦・登録
MWOによる審査を経て認証されると、DMWに推薦され、DMWに受け入れ企業の情報が登録されます。
3、面接
送出機関の求人に集まった候補者と面接をします。
4、在留資格認定申請
採用者の在留資格認定申請を行います。
5、海外雇用許可(OEC)の申請・発行
技能実習生は、在留資格を受け取り後、送出機関を通じて本人がDMWへ海外雇用許可(OEC)を申請し、発行を受けます。
6、入国・受入れ
技能実習生はOECを受け取ってから出国準備をし、日本に入国します。
ベトナム
ベトナムでは、海外で働くベトナム人労働者の権利保護強化を目的として「派遣契約によるベトナム人労働者海外派遣法」が2022年1月1日に施行されました。これにより、ベトナム人労働者の海外派遣に関するルールが大きく変更されました。
⇒技能実習生送出国ベトナムがよくわかる資料をダウンロードする(無料)
技能実習制度におけるベトナム特有の規則
1、手数料の上限
技能実習生が送出機関に支払う手数料の上限が明確化され、以前は給与に関わらず一律の金額でしたが、改正により給与額に応じて上限が設定されました。
・1年契約(移行対象職種以外):給与1ヶ月分以下
・3年以上契約(移行対象職種):給与3ヶ月分以下
2、宿泊費の負担
実習生の住宅費の控除額が「1か月の基本給の15%以下」と定められました。
3、入国前講習費用の負担
介護職種における実習生の入国前講習の企業負担費用額が定められました。
・160時間の講習:1人15,000円以上
・介護職種:入国前の日本語講習の全額(1人100,000円以上)
悪質な送出機関の存在
送出機関の選定ポイントについて解説しましたが、認定された送出機関の中にも悪質なものが存在します。悪質な送出機関の対応の中でも、特に大きな問題として指摘されているのが、不当な手数料の徴収です。
送出機関を選ぶ際のポイントとして「技能実習生の手数料確認」を挙げましたが、なぜ手数料がこれほど重要な問題となるのか、ご存じでしょうか?
送出機関は、監理団体や企業から手数料を受け取るだけでなく、技能実習生からも学費などの名目で手数料を徴収しています。技能実習生の多くは日本よりも給与水準の低い国から来ており、送出機関への支払いのために借金をするケースが少なくありません。そのため、送出機関が過剰な手数料を設定すると、技能実習生の返済負担が重くなり、失踪などのトラブルにつながる可能性があるのです。
⇒「押さえておきたい技能実習のトラブル」とその対応策のわかる資料をダウンロードする(無料)
不当な返済額による問題
悪質な送出機関への支払いのために借金をした技能実習生は、日本での収入の大半を返済に充てざるを得なくなります。借金返済に追われる中で、より高収入を得られる職場を求めるようになり、SNSやコミュニティを通じて魅力的な求人情報に引き寄せられることがあります。
その結果、違法な職場へと誘導され、失踪してしまうケースも少なくありません。
送出機関に支払う費用
技能実習生が送出機関に支払う費用について、法務省が令和3年12月10日から令和4年4月末までの期間に実習生を対象として実施した調査データを見てみましょう。
技能実習生が来日前に送出機関へ支払った費用の総額は、国籍によって大きく異なります。
出典:法務省(技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について)
また、技能実習生が支払い費用の内訳をどの程度理解しているかについては、以下の結果となっています。
出典:法務省(技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について)
適正な手数料の金額とその内訳を、技能実習生に正しく説明することが、入国後の失踪率の低減につながります。受入れ企業様は、送出機関が技能実習生に課す手数料についても確認されることをおすすめします。
まとめ
ここまで、送出機関の役割と選定ポイントについて解説してまいりました。しかし、良い送出機関を企業様で探すことは、簡単ではありません。
企業様にできること。それは優良な送出機関と提携している優良な監理団体を選ぶことです。
どれだけ企業様が技能実習制度の意義を理解し、どれだけ技能実習生を大切にしていても、直接関わらない送出機関が原因で技能実習生が不幸になるなんてことはあってはなりません。
そのためにも、送出機関をしっかり厳選している監理団体を選ぶ必要があります。
エヌ・ビー・シー協同組合の取り組み
わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合も、監理団体としての責任を痛感し、提携する送出機関を厳選しています。技能実習の趣旨をしっかり理解した優良な送出機関を選別し、しかも複数の送出機関と敢えて提携することで、それぞれの送出機関の「レベルの低下」を防いでいます。
「技能実習の成功には優良な送出機関が欠かせない」
これが、わたしたちが長年に渡り技能実習に携わってきて得た結論です。
わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合は、企業様のために、技能実習生のために、これからも真摯に技能実習制度に取り組んでまいります。
⇒エヌー・ビー・シー協同組合の取り組みがわかる資料をダウンロードする
